「端午の節句」と「こどもの日」の違いって?
POINT
- どちらも5月5日のこと。
| 端午の節句 (たんごのせっく) | 男の子の成長を祝うための行事。古くから日本にある。由来は古代中国の宮中行事。 |
|---|---|
| こどもの日 | 男の子・女の子・母親のための祝日。1948年に制定された。由来は大正末期の児童愛護デー。 |

記事の目次
端午の節句とこどもの日の違い
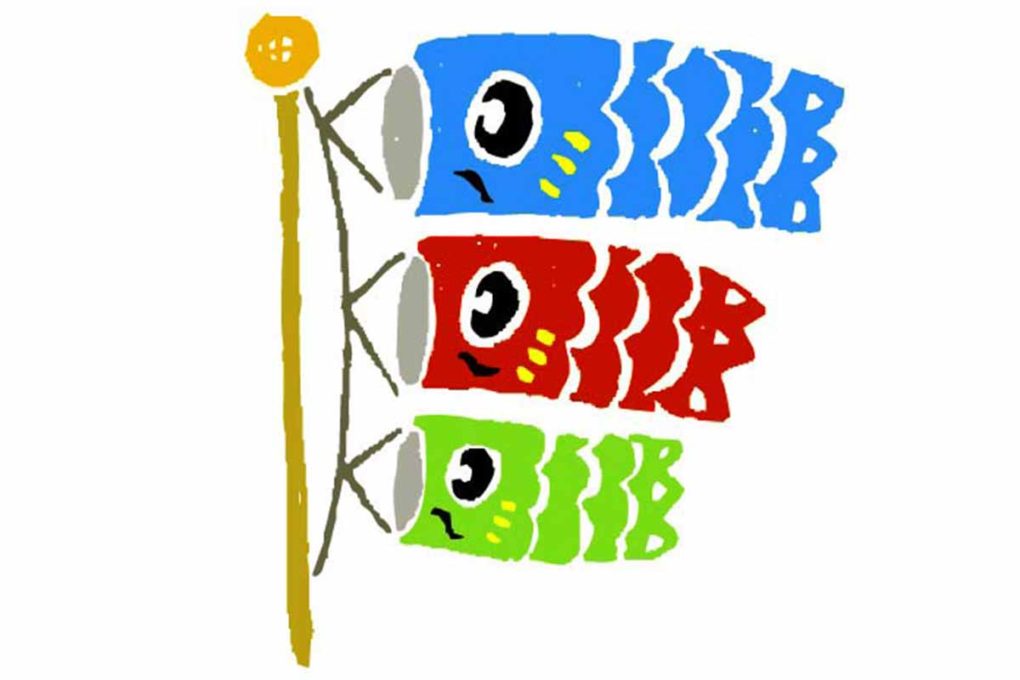
端午の節句(たんごのせっく)とこどもの日は、どちらも5月5日である。日常生活では特に区別する必要はないものの、両者は目的と由来が異なる。
目的
端午の節句は、五節句の一つである。詳しくは後述するが、一般的には男の子の成長を祝うための行事をいう。
- 五節句:年間の節目となる5つの行事
- 1月7日→人日(じんじつ)…七草がゆを食べる
- 3月3日→上巳(じょうし)…女の子の成長を祝う(ひな祭り)
- 5月5日→端午…男の子の成長を祝う・邪気払い
- 7月7日→七夕(しちせき/たなばた)…星祭り
- 9月9日→重陽(ちょうよう)…菊酒を飲むなど
一方で、こどもの日は国民の祝日の一つである。
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
引用:内閣府「国民の祝日について」
ための休日と決められている。つまり子ども(男女)および母親のための日である。
由来・歴史

端午の節句は、古代中国の病気・厄災をはらうための宮中行事に由来する。薬草を摘んだり、魔除けの力があるとされる菖蒲(しょうぶ)を軒先につるしたりして、邪気をはらっていた。
日本に伝わったのは、奈良・平安時代のことである。それ以前から日本に存在した「さつきのもの忌み」(※)と結びつき、日本独自の行事に発展した。江戸時代になると、武家の間で男子の出世祈願をする行事として定着していく。
田植えをする若い女性が菖蒲やヨモギの屋根の小屋にこもり、菖蒲酒を飲むなどして身を清める行事のこと。
端午の節句は「菖蒲の節句」と呼ばれるほど、菖蒲が重んじられている。「しょうぶ」は勝負・尚武に通じるので、男子の成長を祝う行事へと性格が変わっていったと考えられる。
- 端午の節句の風習
- 菖蒲湯に入る
- ちまき・柏餅を食べる
- こいのぼりを立てる
- 五月人形を飾る など
一方で、こどもの日が制定されたのは、1948年である。大正末期に全国で展開された「児童愛護デー」に由来する。
子どもの権利を啓蒙(けいもう)するため、講演会が開かれたり、ビラが配られたりした。現在でも厚生労働省は、こどもの日から1週間を「児童福祉週間」とし、児童福祉に関する啓発活動を行っている。
まとめ
| 端午の節句 | こどもの日 | |
|---|---|---|
| 分類 | 五節句の一つ | 国民の祝日の一つ |
| 目的 | 男の子の成長を祝うため | “こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する”ため(こどもは男女を問わない) |
| 歴史 | 古くからある | 1948年制定 |
| 由来 | 病気・厄災をはらうための古代中国の宮中行事 | 大正末期の児童愛護デー |
